統合失調症、大人の発達障がい、
双極性感情障害(躁うつ病)等、
家族の相談を受け付けています。
NPO法人「わかくさ家族の会」
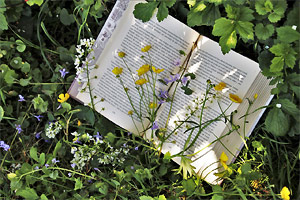
わが子も、もしかして?そんな疑問を持たれた親ごさんの集まりです。
その中で、見えて来ることは、「発達障害」は病気ではなく、生まれ持った障害(未発達なため、苦手な部分を多くもつ特性)の為、投薬治療では治らない事を理解しなければならない。
この事を如何に親御さんに受け入れてもらうかが、この家族会の課題でしょう。
成人になってから、この障害と解かった場合、発達障害というベースに、2次疾患としての精神疾患があったり、多様な投薬による副作用からなる疾患が出たりと、更なるややこしさを伴っているのが、成人の方の「発達障害」だと、思います。
この障害は「早期発見」「早期療育」が、発達への近道です。
その為にも、親御さんの 理解が進まれるように、家族同志の支え合いが大事なように思います。
そして、この会が同じ悩みを持つ親の「居場所」に、なれれば良いと思っています。


リンクリンクリンク
(詳細は会報8月号を参照してください)
憩いの広場のイヴェントについてのお知らせ
2026年の1月から木曜日に、イべントをやりたいと思っています。その内容を少し詳しくお知らせします。ぜひ皆さん来てください。親子でも、子供だけでもいいです。楽しい会にしたいと思っています。
〇 1月15日・・・音楽を楽しむ集い(聞く)
参加したそれぞれの人が、聞きたい曲をスマホ(石橋のもっているもの)かCDでみんなで聞いてみる。例えば美空ひばりの 「柔」(やわら)が聞きたければ、スマホならばグーグルで検索して聞くことができます。CDを持っているなら事務所のカセットCDで聞く子ができます。参加者5人がそれぞれリクエストすれば、一人5分で30分かかります。残った時間はみんなでおしゃべりです。一人2曲以上聞きたい場合は、その時々で対応します。グーグルを使うとほぼ何の曲でも聞く事ができるので便利です。
〇1月22日・・・切り絵で遊ぼう。
白い画用紙に、色折り紙を自分の好きな形に切って、ノリで張り付けて、自由な絵を描こうという会です。このやり方は絵心がなくても、誰でも作る事ができます。ゼロから何かを作り出す楽しみで日頃のストレスを解消しましょう。画用紙、色折り紙、のり、ハサミ、下に敷く新聞紙など、こちらですべて用意します。費用は一切かかりません。出来上がった作品は、壁に貼ってしばし皆さんで鑑賞しましょう。30分から1時間程度でできると思います。
この2つのお楽しみイべントを試しに2日間やってみて、みなさんが楽しめたら、毎月2回、第2第4木曜日に定期的にやろうかと考えています。よろしくご協力お願いします。
講 師: 石橋 理事補佐より
◎憩いの広場のイベントの報告
2026年1月15日に、第一回の音楽を楽しむ会のイベントを開催しました。講師の石橋さんにコメントを書いて頂いたので、掲載します。参考にしてください。
今日は第1回目で、どうなるか不安でしたが、私を含めて7名の方が参加してくれました。
ロック、ポップス、演歌、歌謡曲など色んなジャンルの曲がリクエストされて楽しいひと時を過ごせました。一人で聞くのとはまた違った時間でした。2月もまたやりたいのでどうぞ参加してください。 (音楽を楽しむ集い)
今日は5人の参加でした。初めての試みで、ストレス発散になればと思い企画しました。それぞれ個性のある作品ができたようです。無心でやった方がよかったかなと自分では思いました。来月もやりたいです。 (切り絵で遊ぼう) 担当石橋 誠
(参加者の声)
久しぶりに懐かしい曲を聞くことができて、良かったです。最近じっくり音楽を聴くことがなかったので、とても楽しかったです。
◎次回のお知らせ
〇 2月12日・・・第2回 音楽を楽しむ集い(聞く)
〇 2月26日・・・第2回 切り絵で遊ぼう。
講 師: 石橋 理事補佐
(詳細は会報8月号を参照してください)
憩いの広場のイヴェントについてのお知らせ
2026年の1月から木曜日に、イべントをやりたいと思っています。その内容を少し詳しくお知らせします。ぜひ皆さん来てください。親子でも、子供だけでもいいです。楽しい会にしたいと思っています。
〇 1月15日・・・音楽を楽しむ集い(聞く)
参加したそれぞれの人が、聞きたい曲をスマホ(石橋のもっているもの)かCDでみんなで聞いてみる。例えば美空ひばりの 「柔」(やわら)が聞きたければ、スマホならばグーグルで検索して聞くことができます。CDを持っているなら事務所のカセットCDで聞く子ができます。参加者5人がそれぞれリクエストすれば、一人5分で30分かかります。残った時間はみんなでおしゃべりです。一人2曲以上聞きたい場合は、その時々で対応します。グーグルを使うとほぼ何の曲でも聞く事ができるので便利です。
〇1月22日・・・切り絵で遊ぼう。
白い画用紙に、色折り紙を自分の好きな形に切って、ノリで張り付けて、自由な絵を描こうという会です。このやり方は絵心がなくても、誰でも作る事ができます。ゼロから何かを作り出す楽しみで日頃のストレスを解消しましょう。画用紙、色折り紙、のり、ハサミ、下に敷く新聞紙など、こちらですべて用意します。費用は一切かかりません。出来上がった作品は、壁に貼ってしばし皆さんで鑑賞しましょう。30分から1時間程度でできると思います。
この2つのお楽しみイべントを試しに2日間やってみて、みなさんが楽しめたら、毎月2回、第2第4木曜日に定期的にやろうかと考えています。よろしくご協力お願いします。
講 師: 石橋 理事補佐より
◎憩いの広場のイベントの報告
2026年1月15日に、第一回の音楽を楽しむ会のイベントを開催しました。講師の石橋さんにコメントを書いて頂いたので、掲載します。参考にしてください。
今日は第1回目で、どうなるか不安でしたが、私を含めて7名の方が参加してくれました。
ロック、ポップス、演歌、歌謡曲など色んなジャンルの曲がリクエストされて楽しいひと時を過ごせました。一人で聞くのとはまた違った時間でした。2月もまたやりたいのでどうぞ参加してください。 (音楽を楽しむ集い)
今日は5人の参加でした。初めての試みで、ストレス発散になればと思い企画しました。それぞれ個性のある作品ができたようです。無心でやった方がよかったかなと自分では思いました。来月もやりたいです。 (切り絵で遊ぼう) 担当石橋 誠
(参加者の声)
久しぶりに懐かしい曲を聞くことができて、良かったです。最近じっくり音楽を聴くことがなかったので、とても楽しかったです。
◎次回のお知らせ
〇 2月12日・・・第2回 音楽を楽しむ集い(聞く)
〇 2月26日・・・第2回 切り絵で遊ぼう。
講 師: 石橋 理事補佐

リンク
◎ 2026年2月講演会のお知らせ
日 時:2月5日(木)午後1時~4時
場 所:クリエイトホール 11階視聴覚室
テーマ:「精神に障害のある方が、安心して働くために」
~支援機関の活用と相談のポイント~
講 師:障害者就業・生活支援センタータラントセンター長 加納信吾氏
◎ 2026年3月例会・講演会のお知らせ
日 時: 2026年3月4日(水)13:30~
(開場午後1時~)
テーマ: ・相続について
・八王子市の精神福祉サービス
・保健所の役割
会 場: クリエイトホール11階視聴覚室
講 師:・行政書士 石見光男氏
・八王子市障害者福祉課 木村真也氏
・八王子市保健所 西山香菜美氏
◎ 講演会報告 2025年11月6日(木)家族会事務所
テーマ: 精神疾患を持つ当事者への家族の対応
講 師 : SST リーダー 高森 信子 先生
当日は会場が満席になる程、25名の方々の参加があり、高森先生の言葉に皆耳を傾けていました。最初にコミュニケーションの話をされました。
*良いコミュニケーションとは・・自分の気持ちも言えて、相手の気持ちのわかる人にな
る事。そのポイントとは
(1) 関心表明 → ①視線を合わせる ➁手を使って表現する ➂身を乗り出して話をする
④はっきりと大きな声で伝える ➄明るい表情で ⑥話の内容が適切である事
(2)反復確認 →「の」の字の哲学 <例>おなかすいたよ・・・おなかがすいたの~
(3)話が具体的になるための質問 → 要求は具体的に言わないと伝わらない。
(4)同意ではない共感の言葉 → 言いなりや全て過保護は良くない。
(5)自分の考え → 相手の意見を聞いてから自分の考えも伝える事
<反復確認>ーー言った言葉をくり返す。
➀言葉をくり返す事で正確に聞いた証拠となる。
➁くり返す事で時間がかかり、相手は大切にされたと思う。
➂相手の気持ちがわかってくる。
⓸同じ言葉を言うので、相手の脳に状況変化をおこさない。
~ご家族の方へ~
*親として出来る事・あなたは宝物・生きているだけで立派・気持ちをわかってあげ
る。(薬より効果あり、ビタミン愛)
*人には出来る事と出来ない事があるが「今のあなたを受け入れる、認める。」と相手
の目線に合わせる。(例えば妄想になった時・・・心配だよネ。辛いよネ。)
*「ほめる」「感謝する」を言葉にして伝えましょう。
*思春期は親離れの葛藤の時期。寂しいけれど子離れする自分を育てましょう。自分の
思い通りに仕切らない事。
*相手の気持ちがわかり、自分の気持ちも言えて信頼関係を認めて良いコミュニケーシ
ョンをとりましょう。
【高森先生の言葉の中より】
1.家族が寄り添ってあげる事➨押し付けることはしない。本人が辛そうな時…辛いん
だねと言葉をかける。ダメ言葉は使わない事
2.家の中は明るく
3.良かれと思って家族が助言、忠告、指導➨当事者にとっては大きなストレス症状が
強くなる。
4.信頼関係が壊れると➨本人のストレスが増してくる。
5.親が先走って、してあげる事が➨本人にとっては大きな負担になる。
6.家族が自分の味方だと気づくと➨自分の気持ちを言えるようになる。
7.安心できる居場所が見つかると➨安心感が生まれる。
8.自分が変わるのは難しいが➨不満は胸に収めて演技するのもいいのでは。
9.あなたは大切な人➨あなたが居るからお母さんも頑張れるを伝える。
10.親が変わるという事は➨子供への愛が根底にあるから変わることが出来る。
11.当事者が疲れたりした時に➨期待をする言葉が入ると脳が敏感になり発病する
◎当事者は社会に出る事も叶わずに、家の中で家族と向きあっての日々が続く。親は子供
を落伍者にするわけにはいかないあせりもあって、自分の理解できない妄想や幻聴も否
定してしまう時もあるが、今を受け入れて「よく我慢したネ」「えらいと思うよ」等の 言葉をかけて欲しい。ただでさえ不安なのに、今日一日、生きる事だけで精一杯で、不安な時ほど親のそばが安心します。
★家族が助言、忠告を言わずに、当事者の話をひたすら聞くだけに徹した例です。
娘さんの困りごとが多いので、話を聞いてあげるだけにした。娘さんの問題行動には、
一切触れないのに困りごとが、ひとつ、ひとつ消えていったそうです。
最後に高森先生のロールピアノの伴奏で「明かりをともそう」「バイバイブロンディ」を参加者と一緒に歌い、又 手話も教えて頂き、お困り事の相談も受けてくださり、終了となりました。 (理事 N 記)
2)講演会アンケート
1.高森先生の講演会を何度か聞かせて頂いて、毎回、学び直しが出来て、とても参考になりました。 話をよく聞くこ
との大切さを、あらためて学びました。共感力を意識して、子供と接してゆきたいと 思います。
2.子供の接し方の勉強になりました。来年も絶対に、高森先生を呼んで下さい。遅くまで高森先生のお話をを聞かせて下さり
スタッフの方々、ありがとうございます。
3.大変勉強になりましました。
4.今までの高森先生の後援会とは違って事務所に入ると先生は持ち運べるピアノを弾いて ♪ バイ・バイ・ブロンディ ♪
という歌をうたいましょう、という内容からスタートしました。質問票に対する先生のお話は一生懸命な姿勢で良かったと思 いました。先生は90歳を超えられたと聞きましたが相変わらずの熱弁で安心しました。先生のあきらめない、粘り強い姿勢は勉強になりました。先生のお年を聞いて当事者として長い年月が経ったなあ、と思っております。親子の対話が大事『長所・短所』だとおっしゃいました。実行したいと思っております。
5.3年ぶりにこさせて(参加)頂きました。(高森先生のセミナ-)参考になる事ばかりでした。92歳 、現役すばらしい。先生の情熱伝わってきました。<バイバイブロンディー>の歌よかったです。腰痛もつらかったですが、ミニ体操も教えて下さり、久しぶりに楽しい時間でした。有難うございました。(スタッフの方にも感謝です)
6. 今まで息子の言う事をよく聴いていましたが、いつも私が意見を言っていました。毎年、高森先生のお話を聞いていますが、また今日、反省しました。本人は生きているだけで辛いと思いますが、どうしても将来の事を考えてしまいます。こういう子は先でどうなるのでしょうか。やっぱり心配です。
7.とてもわかり易くて、良かったです。私は35歳で発症しましたが、当時は対人恐怖症がひどくて、やっと60歳になって、ほぼなくなりました。自信の無さがまだ残っています。
8.「の」の字の哲学が難しいです。こちらの気持ちにゆとりがないと出来ないと思いました。なので、親の気持ちにゆとりを持とうと思います。
9.家族の対応を知りたかったので、参加して良かったです。本などで学ぶよりも、やはり生の声で伝えていただくことの大切さを知りました。I love you の手話もまずは試してみようと思います。いつも自分の考えばかりを相手に伝えていたので、自分の行動(言動)も振り返ることができました。講演会を開いていただきまして、ありがとうございました。
10.とても解りやすく、参考になりました。大切なポイント 1~5 を頑張ります。ありがとうございます。
11.いつも参考になるお話を聞くことが出来て現実の話として、伺って良かったです。高森先生、いつもありがとうございます。くれぐれも、御自愛下さいませ。
12. 娘の今を受け入れ、よく聴く様にしたいと思います。
13. 今まで、高森先生のS S T は何度も受けさせて頂きましたが、今回は 又違った、相手の気持ちをわかるためのポイント等、具体的にお話を聞き、私自身、今までの事を反省する機会があり、とてもありがたく、今後に生かして行こうと思っております。(前回の先生のお話を聞き、息子との関係が良い方に変わりました)ありがとうございました。
14. とても大切なお話をありごとうございます。相手の気持ちがわかるためのお話、頭では理解していても実行するのが難しいなと感じました。相手を自分の色に染めない、コントロールしない事、それが寄り添う事、信じる事なのだと思いました。保健所としてそれを相談してくれた方にどう伝えていくか、支援に生かしていくか、もっと考えたいと思います。
15. 先生のお話がとても具体的かつ、実践的でとても参考になりました。ご家族の悩みに寄り添った、かつ当事者本人の視点に立ったお話が心に残りました。保健所でもご相談いただくことが多いので、先生の本日のお話も心に留めながらやっていきたいお思います。貴重な機会をいただき、ありがとうございました。
16. 先生のお話がとてもわかりやすく、具体的な例でわかりやすかったです。
17. 高森先生の講演会も5回目となりました。娘が統合失調症で、医療機関でお世話になり始めて同じく5年目です。5年前と比べると随分人間らしさ(変な言い方ですが)を取り戻したというか、変わったと思います。毎年先生の講演会(お話し)で勉強させて頂き、娘への対応の参考とさせて頂いています。先生の存在は、娘と私の回復へと導いて下さる光となっています。どうぞこれからもお元気でいらして、私たちを導いて下さい。宜しくお願い致します。
18. 高森先生の本を事前に読ませて頂き、親である自分だけでも子供の味方になろう。教え諭すのではなく寄り添い、フィルターを通さずに本人の気持ちを聞こうと心がけてきました。(なかなかうまくできないことが多いのですが)
今回初めて先生の話を伺い、見える世界が温かい色に変わったかのように感銘を受けました。90才を超えられてもなおこの情熱はどこから来るのでしょうか。
来年再来年と又、お話を伺いたいです。自分を少しでも成長できるように頑張ろうと思いました。
講演会アンケート記入者数報告
① 今回の講演会は非常に参考になった・・・16名
② 今回の後援会は家族の役に立つと思う・・12名
③ あまり参考にならなかった ・・・・・・ 0 名
④ 出来れば次回の後援会に参加したい ・・・10名
⑤ 難しくてよく解からなかった ・・・0 名
70歳代の方 ・・・6名 60歳代の方 ・・・5名
50歳代の方 ・・・4名 40歳代の方 ・・・1名
30歳代の方 ・・・1名
男性の方 ・・・1名
女性の方 ・・・16名
統合失調症、大人の発達障がい、双極性感情障害(躁うつ病)などの家族相談
NPO法人 わかくさ家族の会
東京都八王子市新町7-12-203
☎ 090-5422-0942(家族会携帯)
☎ ℻ 042-649-3460(家族会事務所)
✉ wakakusakazokukai@gmail.com